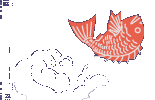女流歌人 原阿佐緒(その4)
阿佐緒は翻意させようとしたが叶わず、帝国大学教授であり、「アララギ」の重鎮である石原を堕落させた女として「アララギ」を破門された。スキャンダルの渦中、第三歌集『死をみつめて』が出版される。世間の注目を浴びて売り上げは伸びたが、「際物」として激しい批判に晒された。「家毎にすももは咲くみちのくの春べをこもり病みてひきしも」「朝の日のいまだもささぬ山かげの小田の畔には霜しろく見ゆ」『死をみつめて』。
恋ばかりが注目される阿佐緒だが、意外にも子どもたちに向ける視線は優しく、多くの歌を詠んでいる。折々の事情で離れて暮らすことが多かった分、「平凡な日常の中の一つひとつの出来事が美しい一枚の絵のように阿佐緒の心に残り続けた」(『第42号原阿佐緒記念館だより』)という。「馬を見に行かなとせがむ児を抱き朝春寒むに霜をふみてし」。しかし、千葉の保田町(現在鋸南町)で石原と暮らす間、子供たちに菓子を送る金すら阿佐緒の自由にはならなかった。
「吾の児に菓子を送りてと友にたのむ手紙かきつつわが泣きにけり」『うす雲』。昭和3年(1928年)9月、阿佐緒は石原に無断で着のみ着のまま「白壁の家」に帰り、新聞各紙は一斉に愛の破局を報じた。翌月、第4歌集『うす雲』を出版。阿佐緒の心はどうしようもなく疲れ果てていた。「曇り風寒けく吹きて大鴉なきつつとまる揺るる梢に」「汐風の吹きなびけたらむ磯山の松の梢みなかたむきて居り」『うす雲』。