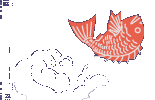女流歌人 原阿佐緒(その2)
明治38年(1905年)7月7日、養嗣子(家督を継ぐ養子)の真剣が肺結核のため夭折。男子の家督相続者がいない原家は、10歳の真剣を阿佐緒の結構相手として養子に迎えていたが、阿佐緒はその事実を「兄」が亡くなってから初めて知った。「わが兄の冷たき石碑見つめつゝ懺悔に似たる涙流すも」。「幸は光は人に盗まれて暗きわが家にのこるかなしさ」。肉親の相次ぐ死。何不自由なく育った「塩屋のおごさん(お嬢さん)」は、いつの間にか「白壁の家」を継ぐべき人になっていた。再び、日本女子美術学校に通い始めた阿佐緒は、教師の小原要逸と出会う。
どういういきさつがあったか分からない。妊娠して初めて、小原に妻子があることを知った。自殺を図ったが果たせず、東京で長男千秋を生んだ。その時、20歳。幼子を抱え、「白壁の家」に帰った阿佐緒を、郷里の人々は蔑視と反感で迎えた。美しい恋に憧れた少女に残酷な現実が突きつけられる。悲しみを紛らわせるように短歌に打ち込み、明治42年(1909年)、『女子文壇』に投稿した一首が「天賞」に認められた。「この涙つひにわが身を沈むべき海とならんを思いぬはじめ」。選者である与謝野晶子を「師の君」と慕い、詩歌結社「新詩社」に入社した阿佐緒。
大正2年(1913年)5月に上梓した処女歌集『涙痕』には、晶子が「純粋の抒情詩を作る人」と評した序文を寄せ、歌を贈っている。「うき恋を根として奇しき百合さきぬ 白きままとの青き涙の」『与謝野晶子』。ナルシステッイクでロマンチックな歌を象徴するように、扉には二十代の阿佐緒の肖像。恋に破れた自分を嘆き、愛への憧れを語った。「生きながら針に貫かれし蝶のごとく悶えつつなほ飛はんとぞする 白百合に似るとはやされ年頃を恋なくて経ぬ寂しくて経ぬ」『涙痕』。大半を叙情歌で占められた『涙痕』にあって、日本画を学んでいた阿佐緒らしく、目に映る景色を色彩豊かに詠んだ歌もある。この年、阿佐緒は「新詩社」を辞し、短歌結社「アララギ」に入社した。「水無月の朝の光にうもれて金砂のごとく棕梠の花ちる」『涙痕』。