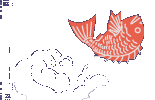女流歌人 原阿佐緒(その3)
心が動かされたからこそ、歌が生まれる。目の前の事象をあるがままに詠うだけで心も伝わる。斎藤茂吉、島木赤彦らの指導を受け、阿佐緒の歌風はより写実的に変化していった。翌年、同郷の庄子勇と結婚。東京の美術学校に通っていた時から思いを寄せてきた相手だった。上京して次男保美を生むと、阿佐緒は産後の身体を休めるため「白壁の家」に帰ったが、東京で暮らす庄子は原家の財産に頼る怠情な生活に溺れていく。旧家を守る母はそんな庄子を嫌い、再び東京に戻ることを許さなかった。会いに来ようともしない夫。だが、阿佐緒は原家の家や土地を売ってでも、一所に暮らしたいと切望する。
生まれたばかりの息子は、父の顔を知らなかった。「家も田も売って都に走らむと夜昼おもへる娘をなげく母」。大正5年(1919年)、第二歌集『白木槿』を上梓。「自序」のなかで、「『白木槿』を分水嶺として新しい道程にのぼりたい心持から」出版したと語っている。自らの心情を赤裸々に詠った歌は減り、日々の風景に感動を見出す歌が目立つ。「初秋の朝の座敷にちらばれる青き木の光り冷たき」「あさあけの家の外行く草刈りの馬の足の音をききにけるかも」『白木槿』。大正8年(1919年)、庄子と協議離婚に至る。わずかか5年の結構生活。
阿佐緒は父親のいない2人の子供を抱えて、再び「白壁の家」で暮らすことになった。大正10年(1921年)7月、新聞各紙で東北帝国大学教授・石原純との関係がセンセーショナルに報じられた。阿佐緒の写真には「石原博士を食った妖婦原阿佐緒」のキャプション。当時、石原には妻と5人の子どもがあった。2人が知り合ったのは、大正6年(1917年)、東北帝国大学付属病院に入院していた阿佐緒を、石原が「アララギ」の仲間として見舞った時だと言われている。思慕を募らせた石原は、執拗に追いかけ、泣き落とし、脅迫的な自殺未遂まで起こした。