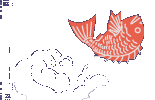化学療法の先駆者 志賀清-その1
明治3年(1870年)12月、仙台で佐藤信の三男に生まれ、名は直吉。父の信は仙台藩の参政で執政書記を務め、戊辰戦争後は東京で廃藩手続きに携わった。長年にわたって収集した戊辰関係の資料を息子の潔が編纂して、明治38年(1905年)『戊辰紀事』として仙台に献じた。仙台幕末史の貴重な資料として評価されている。明治になって武士の身分が無くなった。佐藤家の家計も厳しく、8歳のとき母の実家で藩医の家柄である志賀家の養子となり、名を潔に改めた。旧制一高から東京帝国大学医科大学(現東京大学医学部)に進んで細胞学を先行した。北里柴三郎のペスト菌発見の報告会を開いて、「北里こそ生涯の師」であると心に決めた。明治29年(1896年)次席で卒業して「伝染病研究所」に入り、北里所長から細菌学と免疫学の実地指導を受けた。
北里博士はすでに破傷風の治療法も確立した世界的細菌学者で、その数年前に福沢諭吉が「優れた学者を無為に置くのは国辱である」として、私財を投じて研究所を作り提供していた。志賀の2年後に野口英世が入所した。当時は無口だった英世は同じ東北出身の気安さからか、時々志賀の下宿に訪れていた。明治30年(1897年)夏、国内でも赤痢が猛威をふるい患者数9万人、死者は2万2千人に達した。北里は赤痢の治療法を確立するため、入所2年目の志賀に赤痢の原因究明を任せた。志賀は北里の期待に応えるべく、下宿を引き払い、研究所の片隅に寝床を作って徹夜の研究に打ち込んだ。試行錯誤の末、入院患者の便から本来体内にない菌が見つかった。しかし原因菌を特定するため手を変え実験を何度繰り返しても結果は出ず、迷路の中を進むような作業になる。
冬を迎えた頃、患者の血清に特異な反応をする菌を選別するというアイディアがひらめいた。赤痢菌と思われる菌を培養基に入れて菌を育てた。すると培養基のすべてが血清とのみ特殊な反応を示す事を突き止め、正体のつかめなかった赤痢菌がようやく判明したのであった。12月、日本細菌学会雑誌に初めて赤痢菌発見の報告をし、翌31年にドイツの医学誌に要約論文を発表した。これが世界の学会で認められ、学名を志賀の名をとり「Shigella」(シゲラ)と名付けられ、赤痢研究所の基礎が確立された。志賀は赤痢菌の免疫血清を広く患者の治療に応用し、さらに副作用を軽減したワクチンの製造に成功した。その陰には反応を探るため過激な自家実験もあった。殺菌した赤痢死菌をワクチンとして自分の背中に接種したが、菌の毒素によって10日も苦しんだ経験もあり、その瘢痕は生涯残っていた。