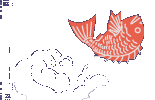郷土の偉人-大槻俊斎(その2)
後になるが宇和島藩で洋式兵学を教えていた大村益次郎(村田蔵六)が、俊斎の屋敷に寄寓し半年ほど直々に学んでいた。そのわずか12年後に起こった戊辰戦争で、大村は新政府軍を指揮し奥羽に討ち入った。歴史の奇縁を感じる。当事人口100万人の江戸は、天然痘が毎年大流行し多くの子供が早死にしていた。嘉永2年(1849年)の初め、予防する種痘苗が長崎に入ったが、幕府の医学は江戸城の漢方医が牛耳っていて、オランダ医学は禁止されていた。だが俊斎は天然痘の惨害を防ぐため手を尽くして痘苗を求め、11月江戸で初めて牛痘法(種痘)の接種に成功した。人々は接種すると牛になると恐れていたが、俊斎は「疑いのない良法である」と確信して多くの小児に接種し、翌年には仲間の医師らと毎日500人の小児に接種を実施した。折から流行していたコレラ患者の救済にも活躍したので、江戸蘭方医の筆頭と称されるようになり、仙台藩医に抜擢される。その4年後にペリーの黒船が来航し国内騒然となると、俊斎は海防に備え銃創の治療要綱を抄訳し、国のために貢献した。
安政5年(1858年)、江戸で大流行中の天然痘に対処するため、伊東玄朴ら優れた蘭方医と種痘所の設置を相談。俊斎が責任者となって幕府から許可され、市中の蘭方医82人が580両もの資金を出し合い、神田お玉ヶ池に「種痘所」を開設した。種痘、診療、鑑定の三部局を設け、日を定めて多くの市民に牛痘接種を献身的に行った。これを見て幕府は種痘を受けるよう市中に呼びかけている。万延元年(1860年)、幕府は種痘の効果を認めて種痘所を買い上げ、幕府直轄の官立「お玉ヶ池種痘所」となり、翌年には「西洋医学書」と改称された。初代所長に就任した俊斎は、種痘と医療教育に解剖を加えた三科にし、西洋医学を教授・研究する国の中心とした。とりわけ人体解剖は当時にあっては驚異的なことで、俊斎の「先見の明」であった。幕府の最高学府創設の功により、将軍の侍医である「欄科奥医師」となり、徳川家重から直々に衣一重と銀を賜る。
幕府は蘭学医に抜群の力量と人望を備えていた俊斎に、西洋医学に関連することしは全て任せた。終始謙虚で後輩友人の面倒をよく見て、西洋医学を目指す後継者の育成に勤めていたが、胃がんに悩み惜しくも文久2年(1862年)4月、57歳の生涯を終えた。明治維新のわずか5年の事であった。墓所は東京都豊島区巣鴨の総禅寺。俊斎亡き後、医学所の二代目頭取に諸方洪庵、三代目には松本良順。ちなみに息子の玄俊は諸方洪庵の娘喜代と結婚し、戊辰戦争で榎本武揚の軍医となり箱舘五稜郭に従軍した。俊斎は牛痘普及の恩人であると共に、「種痘所」が蘭方医学の普及に尽くした役割は大きく、後に「東京大学医学部」に発展して、医学会の発展に貢献した。俊斎は江戸に出たものの、東北弁で言葉が通じず閉口されながらも苦学力行し、周りの人々に支えられ、ついに近代医学への礎を作り多くの人の人命を救った。蘭方医の頂点に立ったのは、生涯、医の道と常に真剣勝負であったからと思える。