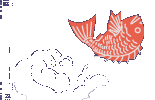郷土の偉人-大槻俊斎(その1)
何時の時代でも治療法が解らない流行病に人は苦しんできた。伊達政宗が右目を失ったのは天然痘(疱瘡)のためで、当時の致死率は40から50%になっていた。天然痘が瞬く間に全国に広がった時、大槻俊斎は江戸で初めて子供たちに種痘を施し多くの命を救った。18歳で江戸へ上がり苦節37年、医師の最高地位に就き蘭方医の第一人者となる。地味ながら誠意溢れる人柄と、旺盛なチャレンジ精神で幕末の西洋医学会の中心人物となった。俊斎は文化3年(1806年)、桃生郡赤井村(現東松島市)、大槻家の次男に生まれ、名は肇、字は仲敏。大槻家は政宗以来白石片倉家の家臣で、分領地赤井の野谷地を180年前に開墾し田畑に仕上げてきた。なお、一関の蘭学者一族大槻玄沢らとはつながらない。
いつも父から先祖の話を聞き、人に役立つ事をと思い学問に励んだ。医師への志強く、反対もあったが兄の援助で江戸に出たのは今からおよそ200年前で、ドイツの医学者シーボルトが長崎の出島に来た頃だ。漢方医官の高橋尚斎の学僕となって苦学力行し、認められて俊斎の名を贈られる。師の勧めで名医と評判の手塚良仙に入門、しゃにむに勉学に励んだ。石巻出身の蘭学者湊長安や蘭方医の足立長寯について蘭学(西洋の学術)の指導を受ける。さらに水沢出身の高野長英と交友し、海外の事情を教えられて洋医学への思いが高まった。俊斎の力量を見込んだ良仙は、学資を援助して長崎へ修行に出た。32歳の時である。長崎で大坂の緒方洪庵らとニューマンの門下生となりオランダ医学の研究に励んだ。
高島秋帆に西洋兵法も学んでいる。当時他地方からの遊学生の殆どは様式砲術と蘭学を学びに行っていたが、東北から長崎に行った62人は医学を目指していた。これは東北人の気質か、人を助ける医学の面で多くの先人を排出した。天保11年(1840年)、4年間の勉学を終えて江戸に帰り、良仙の長女を妻に迎え、神田下谷(秋葉原)に洋医師として開業し念願を叶えた。日本で初めて本格的な外科手術を取り入れ、技術も優れていたので蘭方医としての評判が高まった。数年後、幕政批判で入牢していて高野長英が、牢屋敷の火災で脱獄し俊斎宅へ逃げ込んできた。自訴するよう勧めたが応じず友人の長英に類を与えた。これが発覚し50日の閉門を命じられた。