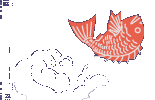仙台味噌(その2)
一方、大豆や米の生産を行っている農家にとって、みそは飢饉対策には不可欠な食糧でした。そのためには三年、五年と保存がきくみそが必要で、独特な作り方が伝わってきました。山吹の花が咲くころになると、屋外に大きな釜を据え、薪を燃やして大豆を煮て、臼でつき、直径二、三十センチのみそ玉をつくります。それに藁を十字にかけて二週間ほど軒先などに吊るして乾燥させます。この間に麹を作り、乾燥したみそ玉を包丁で刻み、塩と麹と水を加え樽に仕込みました。
昭和初期までは飢饉対策としてだけでなく、三度の食事に欠かせない調味料として、みそ汁をはじめ煮物、みそ焼き、みそ漬けなどに使われました。食膳にみその香りが立たない日はないほどでした。そのため、みその仕込みは一度に大豆一俵(製品としては180㎏)とか、四斗樽三本(150㎏)などの例は珍しくありませんでした。三年寝かせて順繰りに「三年みそ」を食べるのが一般的で、仕込みやその後の手入れは手間のかかる仕事でしたが、みそづくりは大切な年中行事でもありました。昭和五十年代には自給率向上を目指して農家が主体となったみその協働加工や委託加工組合が県内各地に組織されました。
これは農家の自家用の委託が中心でしたが、昭和六十年代には水田再編に伴う転作大豆の有効活用と、米消費拡大の一環として販売にも力を入れるようになりました。今では「1.5次産業」として仙台味噌の普及拡大の一端を担っています。この間、日本の食生活は大きく変化し、飽食の時代とも言われるようになりました。食生活が豊かになる一方、米やみそなど日本型食材は食卓から少しずつ姿を消しつつありましたが、最近は健康志向が高まり、その優れた栄養価と、ガン予防効果、コレステロールの抑制、脳の活性化など優れた機能性が見直され、海外にも輸出されるなど、評価されています。