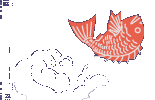成果は客観的で納得できるものを
世の中は今、働き方改革に関する議論が注目されています。実はこの問題は昔からあったもので、特に新しいものではない、とオヤジは言っています。「働き方」というからには、働いている人が、自分の働き方のスタイルを自分の意志で変えようと考え、雇用する側と交渉して決めるのが本来の意味ではないかというのです。いま議論されているのは、「働かせ方改革」で、賃金と労働時間がメインのテーマで、賃金(賃率)をより高く、労働時間をより短くするのが、よい働き方だという固定概念に基づいている。なるほど、賃金や労働時間は、働くことの意味としては大きな要素ではありますが、もっとも重要なことは、働くことで満たされる充実感や、チームワークの形成などを通じて育まれる豊かな人間関係の構築ではないでしょうか。こうした視点が欠落しているため、当の働き手である労働者が醒めた目で見ているため、本当の議論が盛り上がらないのではないかと危惧しています。日本の卸・小売業やサービス業の生産性が諸外国に比べ劣っているのも、ここに問題があるような気がします。
話は変わりますが、わが家のオヤジは、多少報酬が高くても、定型的な仕事は好まないというあまのじゃくなところがあります。そのオヤジが取り組んだ仕事の中で、もっとも難しかった仕事の一つは、企業の賃金表を作る仕事だったようです。その難しさというのは、ズバリ言って、「成果は客観的で納得できるもの」にすることです。つまり、企業で賃金表を作るということは、成果を上げた者により高い賃金を支払うというシステムを、経営者側だけではなく、労働者にも納得がいくものにするということですから、その「物差し」を見つけるのに苦労する。ある企業では、もっとも売り上げを上げた者が賃金も高い。つまり、売上の実現と賃金の高さはほぼ一致している。しかし、これが付加価値と賃金では、まったく相関関係(連動性)が見られないことが判明した。別の言い方をすれば、本当に「会社に貢献している人」は誰なのかを測定する物差しが全くできていないわけです。もっとも、労使が認める客観的尺度を見つけ、それを賃金制度に組み込むことは不可能に近いかもしれません。
例えば、野球のピッチャーが1点しかとられなくても、味方が0点しか取れなければ負け投手になってしまう。また、サッカーでは、直接ゴールを決めた者だけが評価されるのでは、本気でアシストする選手はいなくなるが、これをどう評価するか。予算消化率が次年度の予算獲得のための評価指標になっているなども、本末転倒で、本来ならば少ない予算で目的に沿った工事を完工する部署を高く評価すべきなど、企業以外でも成果と評価の関係は客観性に欠けていることが多い。とはいうものの、すべての成果が観測可能で客観的な評価に結びつくものではないが、少なくとも、コストとして支出する側と、これを所得として生活の糧にする側が納得する接点を模索するという姿勢は必要である。これを見つけるのがむずかしいということと、むずかしいからやらなくてもいいということは同じではない。現在の枠組みの中でも、労使の姿勢が同じ方向を目指しているなら、「何をもって当社の成果とするか」は、客観的で納得のいくものがきっと見つかるはずだと信じたい。真の「働き方改革」とは、まずそこに気づくことではないでしょうか。